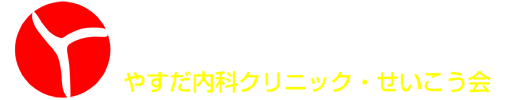心臓弁膜症とは
心臓弁膜症とは、心臓の4つの弁(大動脈弁、僧帽弁、肺動脈弁、三尖弁)のいずれかに障害が生じる疾患です。心臓は全身に血液を送り出すポンプであり、これらの弁は血液の流れが一方通行になるように機能しています。心臓が1回拍動するたびに、各弁は1回開いたり閉じたりしています。
弁の機能異常は大きく分けて2種類あり、弁がきっちりと閉じない場合(閉鎖不全症、逆流症)と開かない場合(狭窄症)があります。これにより、息切れや疲労感、胸痛などの症状が現れることがあります。早期発見と適切な治療により、合併症の予防や生活の質の維持が期待できます。
当院で行う心臓弁膜症の診断・治療内容
—診断検査
心臓弁膜症の診断では、まず聴診による心雑音の確認を行います。特徴的な心雑音は弁膜症を示す重要な手がかりとなります。さらに詳しい状態を把握するために、心エコー検査を実施し、弁の動きや血流の状態、心臓の大きさなどを評価します。エコー検査では心臓内の血液の流れをカラーで表示することもでき、狭窄や逆流があれば一目瞭然に分かります。
また、胸部レントゲン検査で心臓の大きさや肺うっ血の有無を確認し、心電図検査で不整脈などの合併症を調べます。必要に応じて血液検査も行い、心不全の程度や原因となる疾患の評価を行います。これらの検査結果をもとに、適切な治療計画を立てていきます。
—内科的治療
心臓弁膜症に対する内科的治療は、症状の程度や原因に応じて行います。軽度から中等度の弁膜症では、主に薬物療法を中心とした治療を行います。利尿薬は体内の余分な水分を排出し、心臓の負担を軽減します。血管拡張薬は血管を広げることで心臓の仕事量を減らし、抗凝固薬は血栓形成を予防します。
また、不整脈がある場合は抗不整脈薬を使用することもあります。定期的な通院により、症状の変化や薬の効果、副作用などを確認しながら治療を進めていきます。生活習慣の指導も重要な治療の一環として、適度な運動や塩分制限などについてもアドバイスします。
—専門医との連携治療
症状が進行した重度の弁膜症や、内科的治療で症状の改善が見られない場合は、専門医と連携して外科的治療を検討します。当院では患者様の状態に応じて、適切な専門医療機関への紹介を行っています。
外科的治療には弁形成術(自己の弁を修復する方法)と弁置換術(人工弁に置き換える方法)があり、患者様の年齢や弁の状態、全身状態などを総合的に判断して最適な治療法を選択します。近年では、カテーテルを用いた低侵襲治療(TAVI/TAVRなど)も普及しており、高齢者や手術リスクの高い患者様でも治療が可能になっています。
—定期的なフォローアップ
心臓弁膜症は慢性的な疾患であり、定期的な経過観察が必要です。当院では定期的な診察と検査を通じて、弁膜症の進行状況や合併症の有無を確認します。特に心エコー検査は弁の状態や心機能を評価する上で重要な検査であり、症状や重症度に応じて適切な間隔で実施します。
また、服薬状況や副作用の有無、日常生活での注意点なども確認し、必要に応じて治療内容の調整を行います。患者様の生活の質を維持しながら、長期的な健康管理をサポートします。
主な検査内容

—心臓・循環器系検査
心電図検査(12誘導心電図)
心エコー検査(心臓超音波検査)
胸部レントゲン検査
ホルター心電図(24時間心電図)
血圧測定(通常の血圧測定)
—血液・生化学検査
BNP測定(心不全の指標)
血液一般検査(貧血の評価など)
腎機能検査(BUN、クレアチニン)
電解質検査(ナトリウム、カリウムなど)
凝固系検査(PT-INRなど、抗凝固療法の管理)
—その他の検査
尿検査(尿蛋白、尿潜血など)
体組成測定(体重管理の指標)
心肺運動負荷試験(必要に応じて)
早期発見のポイント
初期には自覚症状はなく、検診で心臓の拡大や心雑音を指摘されて偶然に発見される場合も少なくありません。しかし、進行すると心不全や不整脈の症状が出現します。特に、以下のような症状がある場合は早めに受診しましょう。
体を動かしたときに動悸や息切れを強く感じる
体重が急激に増える(むくみによる)
足や手首にむくみが生じる
夜間に息苦しくて横になれない
これらの症状がある場合、心臓弁膜症を含む心不全の可能性があり、詳しい検査が必要です。また、不整脈から弁膜症が発見される場合もありますので、脈が乱れていないかを自分で確認してみるのもよいでしょう。
予防の基礎知識
高齢者の心臓弁膜症が増加しており、動脈硬化が原因ともいわれています。予防のためには以下の点に注意しましょう。
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の管理
適度な運動の継続
バランスのとれた食事療法
禁煙
すでに弁膜症を指摘されている方は、自覚症状がなくても定期的に心電図やエコー検査を受けることが重要です。また、歯科治療(特に抜歯)の際には事前に主治医に相談し、必要に応じて抗生物質の予防投与を受けることで、感染性心内膜炎を予防することも大切です。