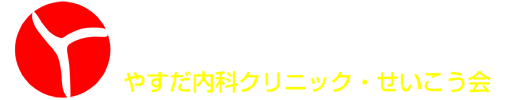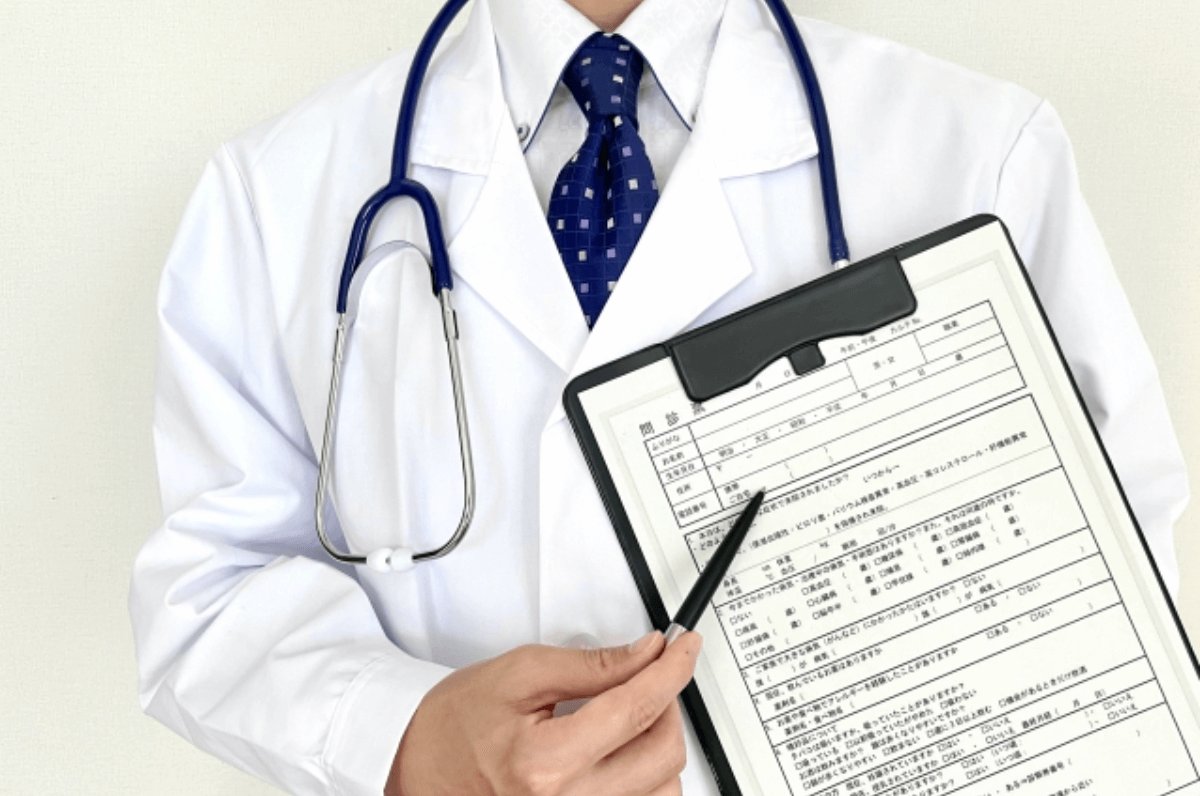心不全とは
心臓は私たちの体の中心となるポンプ機関で、絶え間なく全身に血液を送り続けています。この大切なポンプの働きが弱まり、体の各部位に必要な酸素や栄養素を十分に届けられなくなった状態を「心不全」と呼びます。これは特定の病気の名前ではなく、様々な心臓疾患(弁膜症や心筋梗塞など)によって引き起こされる機能低下の状態を表しています。症状が進行すると、息苦しさやむくみ、疲労感などが現れ、日常生活に支障をきたすようになります。
長期間にわたって徐々に進行する場合は「慢性心不全」と呼ばれ、心臓病の最終段階として生命への影響も大きくなります。近年の医学研究では、単なる心臓の機械的な問題だけでなく、体内の様々なホルモンバランスにも影響を与える複雑な症候群であることがわかってきました。
一般の方にとっては、「心臓が疲れて十分に働けなくなり、体中に影響が出ている状態」と理解していただくとわかりやすいでしょう。
当院で行う心不全の治療内容
—診断・検査
心不全を疑う症状がある場合、まずは詳しい問診と身体診察を行います。その後、血液検査や心電図、胸のレントゲン撮影などの基本検査を実施します。
特に重要なのは、心臓から分泌されるBNPという物質の血中濃度測定です。この値が高いほど心不全の可能性が高く、重症度の判断にも役立ちます。また、心臓の動きを詳しく調べる超音波検査(エコー)は、心臓の大きさや収縮力、弁の働きなどを評価する上で欠かせない検査です。
—薬による治療
心不全の治療では、適切な薬の継続的な服用が鍵となります。処方された薬を自己判断で中止すると症状が悪化する恐れがあるため、医師の指示に従った服薬が大切です。
体内の余分な水分を排出する利尿剤や、血管を広げて心臓の負担を軽くするACE阻害薬、心拍数をコントロールするβブロッカーなど、様々な薬を患者さんの状態に合わせて組み合わせて使用します。
これらのお薬は症状を和らげるだけでなく、心不全の進行を抑え、生活の質を向上させる効果も期待できます。効果が現れるまで時間がかかるものもあるため、根気強く続けることが重要です。
—食事の管理
軽度の心不全では、極端な制限は必要ありませんが、塩分を控えめにすることが基本です。一日の塩分摂取目標は約6〜7g程度に抑えるとよいでしょう。高齢の方では過度の塩分制限によって食欲不振や栄養不足を招くことがあるため、バランスが大切です。体重が多い方では、適正体重を目指した食事量の調整も有効です。
塩分の取りすぎは体内に水分をためこむ原因となり、むくみや息切れを悪化させます。普段の料理は薄味を心がけ、加工食品や外食が多い方は特に注意が必要です。
—生活習慣の改善
タバコは心臓に大きな負担をかけるため、心不全の方は禁煙が必須です。禁煙によって再入院率や死亡リスクが低下することが証明されています。お酒は特に心臓の筋肉に悪影響を与えることがあるため、控えめにするか、医師の指示があれば完全に避ける必要があります。
症状が悪化している時期は安静にすることが必要ですが、安定期には適度な運動が推奨されます。過度の安静は逆に体力低下を招き、症状を悪化させることもあります。
入浴時は熱すぎるお湯は避け、ぬるめのお湯(40℃前後)に浅く浸かり、長湯はしないようにしましょう。熱いお湯は心臓に負担をかけます。
毎朝の体重測定も大切なセルフケアです。短期間で2kg以上体重が増えた場合は、体内に水分がたまっている可能性があり、症状悪化の前兆かもしれません。
—在宅での医療サポート
当院では在宅療養を希望される心不全患者さんのために、訪問診療サービスを提供しています。定期的なご自宅への訪問で、体調の変化を早期にキャッチし、薬の調整や生活指導を行います。
急な症状の変化にも24時間体制で対応可能です。
特に高齢の方や何度も入退院を繰り返している方にとって、住み慣れた自宅で適切な医療が受けられることは、身体的にも精神的にも大きなメリットがあります。ご家族の負担軽減にもつながるよう、多職種による包括的なサポートを心がけています。
主な検査内容
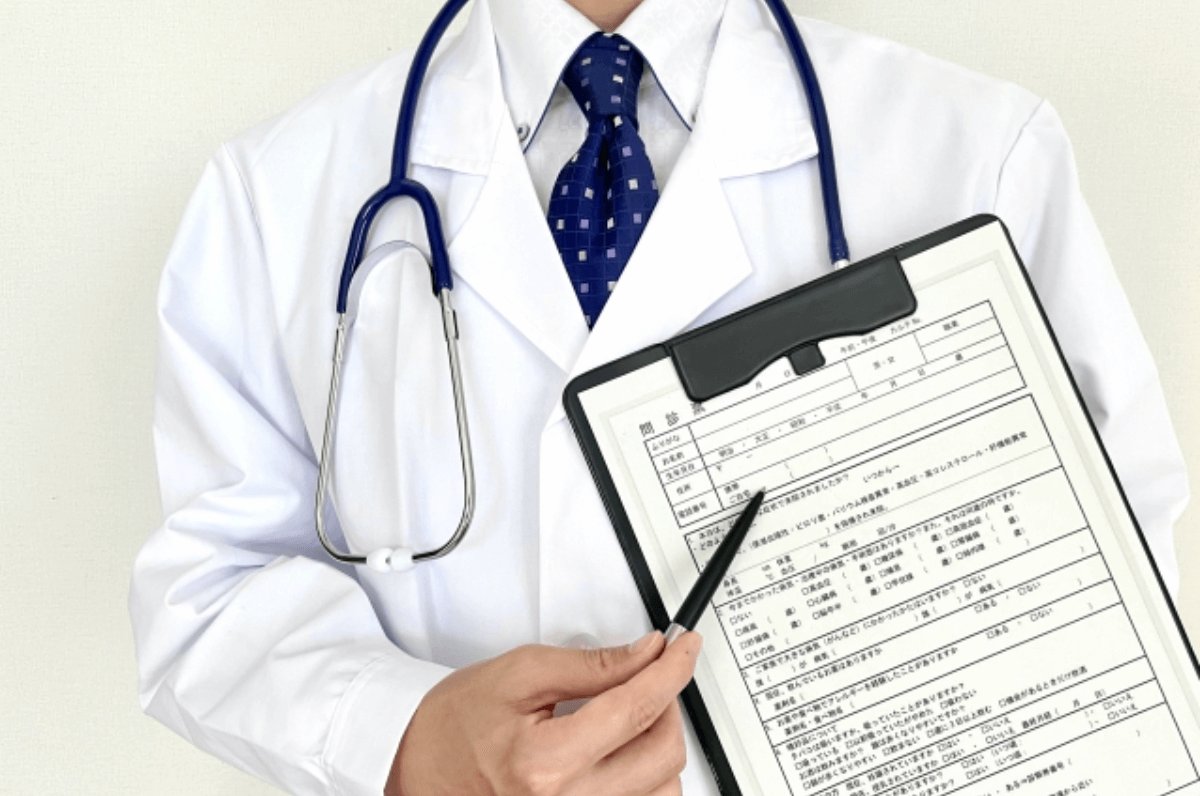
—血液・尿検査
心臓から分泌されるBNP値の測定(心不全の有無と重症度を判定)
肝臓・腎臓の機能検査(臓器への影響を評価)
血液中の成分バランス確認(ナトリウムやカリウムなど)
貧血の有無のチェック
尿検査による腎機能の評価x
—生理機能検査
心電図による心臓のリズム異常や虚血の確認
胸部レントゲンによる心臓の大きさや肺の状態チェック
心臓エコーによる心臓の収縮力や弁の状態評価
終日心電図で日常生活中の不整脈をチェック
自動血圧計による血圧変動の確認
—その他の検査
呼吸機能検査で肺の状態を確認
6分間歩行で運動能力を評価
体重の継続的な記録と変化の観察
必要に応じた精密検査(心臓カテーテル検査など)
睡眠時の呼吸状態の評価